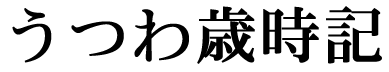九月と云うのに暑い日がつづいています。
空の雲の色には、どことなく真夏のころとは違った気配が感じられますが、テーブルの上は変わり映えのしないままでままです。
染付の鉢をならべて、模様ばかりは多少なりとも秋を思わせようと苦肉の策を講じています。
*
手前、右側の子持ち茄子の向付に南瓜の炊いたの。
左の葡萄模様の鉢に素麺一口。
中央の吹き墨の碗に青豆豆腐です。新豆腐という秋の季語がありますが、スーパーで買ったのではあまりピンときませんね。
吹き墨の碗は先だって、久しぶりの雨の日に、ようやく焼いたのですが、なぜか失敗してしまいました。普段より1.5倍くらい時間がかかったうえに、歪んだり切れたりの散散な結果でどっと疲れが出ました。
*
その向こう、隠れて見えにくいですが,風鈴模様のそば猪口に酢の物。秋の風鈴はわびしいものですが
*
黒鉄の秋の風鈴なりにけり 飯田蛇笏
*
の、句には、凛とした風格が感じられます。
*
芙蓉手の鉢にウナギの蒲焼。山椒の青い実がかわいかったので添えてみました。どんなに暑くても植物は季節を忘れないのですね。
その向こうの芙蓉手の菓子鉢に、戴き物の無花果。
*
無花果を割るむらさきの母を割る 黒田杏子
*
以前俳画の時にも書きましたが、こわい句ですね。
*
この句ではありませんが、黒田先生の句皿用に、小さな皿立てを買いました。やちだも という木だそうです。やちは谷地、湿気の多い場所のことですから、そういう土地に生えるたもの木で、建築にもつかわれる高木です。青だも などはトネリコの仲間、だそうですが、やちだもは木犀科とか。
*
さやけしや皿立てにする木を名指し おるか
*20250901