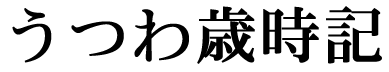見上げると,高層の絹雲、羊雲、鰯雲、空には、秋が来ていました。
秋の味もでそろってきたところで、向こう付けに、あれこれ盛り付けてみました。
*
手前の長丸皿に、木耳(きくらげ)入り卵焼き。木耳は好きなんですけど、こういう卵焼きにしろ、茶わん蒸しにしても卵と組み合わせた食べ方しか思いつかなくて。これでこそ木耳だ!という食べかたをみつけたいものです。
絵はやんちゃな虎の子が遊んでる図です。絵柄は他にもいろいろあります。
*
その左、荷葉型の小付けに普通のお豆腐と胡麻豆腐 のヒジキ添え。卵豆腐と胡麻豆腐をならべて「金銀豆腐」と呼んだりしますが、この場合は何といえばよいのでしょう。白銀豆腐(?)。秋の季語に「新豆腐」がありますが、いつものパック詰めの御とうふです。その年の新しいお豆で作られたお豆腐、さぞかしおいしかったことでしょうね。
*
中央の菊の葉形の向付けに鮭とアスパラガスのバター・ソテー。その左の、四方豆鉢はごらんのとおり炒り胡麻だけ。瓢箪が、見込みに二つ、外側に四つ描いてあるので、六瓢→「むびょう無病息災」とかけてあります。瓢箪がそもそも縁起の良いものですし。赤い瓢箪はいかにもめでたい感じがします。
*
其の向こう長四角というより平行四辺形の平鉢に蓮根のミンチ挟み焼き。図柄は「夕照帰帆図」何となく秋らしい図柄だと自分では思っているのですけど。
*
赤絵の菊の花模様の片口に煮物。砧形の徳利に紅葉。砧打つ音の寂しさは秋ならでは、ということで砧打つは季語になってます。新古今集にも
*
み吉野の山の秋風さよ更けて故郷寒く衣打つなり 参議雅経
*
等の歌があります。上の歌には砧はでてきませんけど。
*
そして赤に塗籠めた木の葉形の大皿。秋になったら果物が少しは安くなってくれるかと思いましたが、どうもそうでもないみたい。
*
今年、山ではドングリなど熊のえさが不作だそうで、熊の被害が増えています。家の裏手にある柿の木に、今年は確実に来るだろうと思って気を付けてはいますがちょっと心配です。
*
熊はかつては山の王であり神だった。人と熊の間には、なにか敬いあう間柄みたいなものがあって敬して遠ざける関係だったと考えられています。
宮沢賢治の小説「なめとこ山の熊」の猟師小十郎と熊たちの関係ように。
*
小十郎は生活のために熊を殺しまくっていますが心の中では「すまない」と思っているし、熊の方もその気持ちがわかっていて、小十郎が死んだとき、彼を祀るように熊たちが取り囲む。
*
世界中で熊は山の神として祀られています。ラスコーの洞窟壁画の中にも熊は描かれています。アムール川周辺のイヌイットの方たちの絵の中では、熊がまるで、南米のマヤ人の人身御供の若者のように、その時が来るまで王様のように大切に扱われ、特別な死を迎える手順が描かれています。そうやってあの世に行って他の熊たちの魂にとりなしてもらえる、と考えていたらしい。
*
こうなったら、いっそ熊祭りでもしないといけないのかもしれませんね。そうして、満足して立ち去ってもらえるように。
⋆
⋆
社(やしろ)荒れうまく回らなぬ木の実独楽 おるか
⋆
20251006